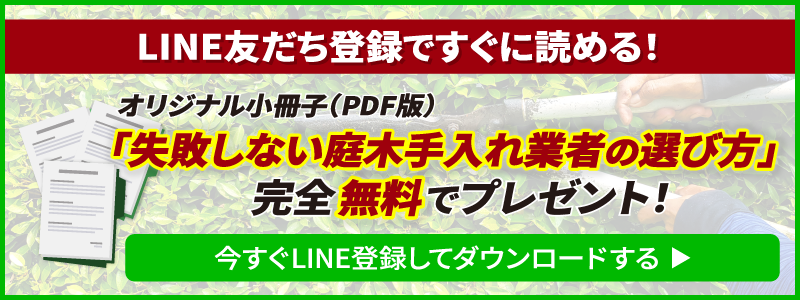第一話 沈黙する梅

「もう、根元から切っておしまいなさいな」
縁側で茶を啜りながら、佐都子さんは吐き捨てるように言った。視線の先には、庭の隅で黒い塊のように枝を絡ませた、一本の梅の古木がある。
「主人が亡くなって五年、一度も花が咲かないの。毛虫はつくし、日当たりは悪くなるし。あの人も、もういらないって言ってるのよ」
七十を超えた彼女の声には、諦めと、ほんの少しの苛立ちが混じっているように聞こえた。
私は黙って、その「黒い塊」に歩み寄った。 ゴツゴツとした幹に手を当てる。冷たいが、死んではいない。 ただ、息ができないのだ。無数に伸びた若芽が互いの光を奪い合い、懐(ふところ)の空気を淀ませている。
「奥さん。こいつはまだ生きてますよ。ただ、ちょっと服を着込みすぎただけだ」
佐都子さんは鼻で笑った。「お上手ね。でも、もういいの」
私は脚立を立てた。返事は待たない。 鋏(ハサミ)を腰から抜く。カチャリ、という音が、静まり返った庭に響いた。
職人の仕事は、木と会話することだ。 『苦しいか』と問えば、木は『ここが重い』と枝を垂れる。 私は余計な言葉の代わりに、鋏を入れる。
パチン。パチン。
混み合った枝を透かすたび、地面に木漏れ日が落ちる。 風が通り抜け、幹が深呼吸をする気配がする。 込み入った枝を外し、空へ向かう勢いのいい枝を残す。ただそれだけのことで、木は本来の気品を取り戻していく。
一時間ほど経った頃だろうか。 黒い塊だった梅は、すらりと背筋を伸ばした老紳士のような姿に変わっていた。
そして、その作業の最中、私は「あるもの」を見つけた。
「……奥さん、ちょっと」
私が呼ぶと、佐都子さんは億劫そうにサンダルを突っかけ、庭に降りてきた。 そして、私の指差す先を見て、息を飲んだ。
太い枝の股に、針金でくくりつけられた古い木札が隠れていたのだ。 枝葉の影になり、今まで誰の目にも触れなかった場所。
『金婚式 ありがとう』
マジックの文字は薄れて消えかかっているが、最後に書かれた日付は、ご主人が亡くなる半年前のものだった。
「……あ」
佐都子さんの喉から、小さな音が漏れた。 震える指先が、木札に触れる。
「あの日……お父さん、脚立に乗ってごそごそやってたわね。何してるのって聞いたら、『毛虫をとってるんだ』なんて嘘ついて……こんなところに、隠してたの」
ボロボロと、佐都子さんの目から涙がこぼれた。 私が枝を透かさなければ、この言葉は永遠に闇の中で朽ちていっただろう。
「日が当たるようになりました。来年の二月には、きっと咲きますよ」
私がそう伝えると、佐都子さんは涙を拭い、綺麗になった梅の木を見上げた。 その横顔は、少しだけ少女のように見えた。
「……切らなくて、よかった」
佐都子さんは、綺麗になった梅の木を、まるで亡き夫に触れるように優しく撫でた。
私は道具を片付け、深く一礼した。
「花が咲いたら、また呼んでください。花後(はなご)の剪定も大事ですから」
帰り道、腰袋の鋏がカチャリと鳴った気がした。 『いい仕事だったな』と言われたようで、私は少しだけ胸を張った。